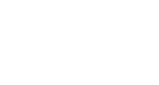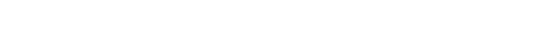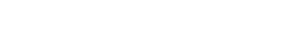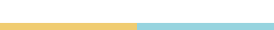その絵が歌い出す / 栄光の架橋 アレンジノート
音程 : ⬛︎ ⬛︎ ⬛︎ 3
リズム: ⬛︎ ⬛︎ ▪️ 2.5
歌詞 : ⬛︎ ⬛︎ 2
技術 : ⬛︎ ⬛︎ ⬛︎ ⬛︎ 4(男声合唱セクション)
今回最もこまり果て、実の所アレンジで完成が一番最後となった。というのは、「この曲はもうこのままでいい」からだ。
アートというのは人の内面を現実世界に表出させる作業だ。風景画であっても、とある風景が「自分の心の中にはこう映っている」という世界を描き出す。
(僕の理解では)すでに美しい富士山を水彩画にするのは、実物の富士山の美しさを超えたいからではなく、「自分の魂にとって富士山がどんな存在であるか」を表出するためだ。
合唱アレンジというものがアートであり得るのは「僕の魂にとってはこの曲がこう鳴っているのがかっこいい/美しいんだ!」と思える瞬間だ。建前を言うようだが、作り手自身の感動がないアートというものは存在しない(他人にはその感動の有無の判別がつかないことは大前提としても)。
栄光の架橋は原曲のままでいい。というのが僕の最初の感想だった。僕自身が過去にこの曲に入れ込んだことがあったわけではないが、改めて原曲を聴くにつけ、完成形としてギターの弾き語りで、それをみんなでユニゾンや、原曲のゆずの2声のハモリで歌えば良い、と感じた。
いじったところで原曲の輝きを削ぐだけのアレンジに意味はないし、そういう意味のない合唱アレンジもどこかで聴いたことがあるような気がする。そういう意味で、これをいじってアートになる感覚が当初は浮かばなかったのだ。
アートというのは、「それ以上さわらないこと」が答えの時もある。コース料理の中に、一つのいちごをそのまま皿に出す一品があってもいいのと同じだ。
だがいやいや、今回の僕の任務はそれではない。新たに出会う人々がそこにいる以上、その人たちにしか出せない音がある。そして、その出会いの輝きを強調してやるようなアレンジが必ず存在する。
新しい演奏環境があるなら、そこに相応しい新しいアレンジが必ずある。
(自分の曲のアレンジを許さないという一部の作曲家の考えを、僕は尊敬しない。)
こういう状況でイメージを湧き立たせる手法の一つはビジュアライズ/映像化だ。
今この瞬間に、この顔ぶれでしか出来ない音、存在するはずのその音が出ているシーンを映像化することで、その映像がどのような歌を歌っているかに想いを巡らせる。
歌い手の顔ぶれの確定前であったが、とにかくも男女比をスタッフに聞くと、どうも男性が最低でも半数となりそうだ。
思い巡らせるうちに一つの絵が浮かんでくる。元オリンピアンや巨大な敵に挑み続けるレスラーなどの屈強な男たちが足を開いて立ち並び、その中に一歩前に出る者がいる。その一人が物語を語り始め、背後の男たちがその物語をサポートする。何となくラグビーニュージーランド代表のハカを思わせるその絵が頭の中で最初の音を出してきた。それを声に出してDAWに録音し始めて作業が始まる。
男性陣が作ったパワーにやがて女性陣が合流してきて和音が広がり、全体像が組み上がってくる。
この曲には、最終的には皆が共に歌えるように、ということだと思うが、一人称(僕、私、俺)がない。男、女、アスリート、応援者、どの視点からでも自分を中心に歌詞を歌えるようになっている点において、見事な作りだ。
合唱に不慣れなアスリートの男性たちを3声に分けて「男声合唱」をさせるリスクは、十分に心配なものだった。でも、合唱として超えなくてはいけないハードルも必要だ。
内心、後で簡単に作り替えなくてはいけないかも、というセイフティネットを張って臨んだが、アスリートたちには無用だった。
収録日、あの絵のままが形になった歌唱の瞬間と、歌い切った後のアスリート達の顔が忘れられない。
カメラのないところでも練習を重ねたメンバー達に感謝したい。
また、この場を借りて、メンバーを鼓舞し一つにまとめてくれたノルディックスキーの荻原次晴さんと、プロ歌手の声をもって音をしっかり支えてくれたブラジリアン柔術の渡辺ナオヨシさんに特段のお礼を伝えたい。
楽譜販売 CLICK!